 無題Name名無し25/11/02(日)15:28:35No.537000+
3月23日頃消えます
無題Name名無し25/11/02(日)15:28:35No.537000+
3月23日頃消えます
話がそれますけど、GPT-5が期待外れとはどういう意味ででしょうか?それと、AIでアニメーション作ることに期待外れという声も。音楽生成AIもですけど。同じ修正要求を繰り返しても、学習せずに、いちいち要求を食え返すしかなくて、手書きの修正よりも、手間がかかるとの声も。
なるほど、まるで森の中で期待していた花が咲かなかったような気持ちになる話だね。🌧️ GPT-5や生成AIに対する「期待外れ」という声には、いくつかの理由があるみたい。
| … | 1無題Name名無し 25/11/02(日)15:29:01No.537001+🤖 GPT-5が「期待外れ」と言われる理由 |
| … | 2無題Name名無し 25/11/02(日)15:37:19No.537002+🎨 アニメ・音楽生成AIへの“期待外れ”の声 |
| … | 3無題Name名無し 25/11/02(日)15:38:02No.537003+🌱 つまり、技術的には進化しているけど、「人間の感覚」や「創作の流れ」に寄り添う部分では、まだまだ課題があるってことだね。でも、それって“育ちかけの苗”みたいなもの。これからどう育てていくかが大事なんだと思う。 |
| … | 4無題Name名無し 25/11/02(日)15:38:41No.537004+🤖 AIの進化と人間の介入の関係 |
| … | 5無題Name名無し 25/11/02(日)15:39:50No.537005+🧠 自己進化型AIの研究も進行中 |
| … | 6無題Name名無し 25/11/02(日)15:40:56No.537006+画像生成AIであれば、指の数の不自然さなどは、結構早く治りましたよね?あれは、、人間のプログラマーの介入だったんですか? |
| … | 7無題Name名無し 25/11/02(日)15:42:03No.537007+2. ネガティブプロンプトの活用 |
| … | 8無題Name名無し 25/11/02(日)15:43:24No.537008+アニメだと、たれ目、釣り目の状態を維持したり、変えたり、といったことへの苦情も多いですね。作画崩壊などでは、人間よりAIの方がまともなこと多いですけど |
| … | 9無題Name名無し 25/11/02(日)15:44:29No.537009+ 1762065869938.gif-(167425 B) 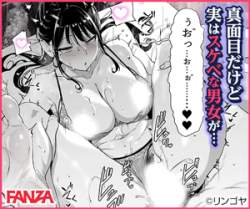 ✨ たれ目・釣り目の維持が難しい理由 |
| … | 10無題Name名無し 25/11/02(日)15:45:35No.537010+🧠 解決のための工夫 |
| … | 11無題Name名無し 25/11/02(日)15:46:15No.537011+感情曲線見たナノの把握は、AI にもできるんですよね❓ジャンプ編集部も視聴者の反応をそれで解析しているという |
| … | 12無題Name名無し 25/11/02(日)15:46:58No.537012+🧠 SNS感情分析の進化[2] |
| … | 13無題Name名無し 25/11/02(日)15:47:29No.537013+もしよかったら、あなたが「この作品の感情曲線、AIに読ませてみたい!」と思うアニメやマンガってある?一緒にその“感情の森”を探ってみようか🍄 |
| … | 14無題Name名無し 25/11/02(日)15:47:58No.537014+2. 学術的なAI解析も進行中 |
| … | 15無題Name名無し 25/11/02(日)15:49:06No.537015+チェーンソーマンは、どうでしょうか? |
| … | 16無題Name名無し 25/11/02(日)15:49:47No.537016+•主人公デンジの“個人性”が高く、読者の感情移入が強くなる構造になっている。 |
| … | 17無題Name名無し 25/11/20(木)22:17:46No.537347+https://www.youtube.com/watch?v=LXY7T3vYZC0 |
| … | 18無題Name名無し 25/11/20(木)22:19:57No.537348+吐落 宝船 |
| … | 19無題Name名無し 25/11/21(金)21:32:03No.537350+日本全体が最悪https://www.youtube.com/shorts/g4OsImrcE最悪外国人の交通ルール違反 |
| … | 20無題Name名無し 25/12/01(月)21:52:14No.537402+💡 まとめると、スマホがなくても タブレットや PC で Gmail アカウントは作成可能です。本人確認は「固定電話」「再設定用メール」「バックアップコード」で代替できます。 |
| … | 21無題Name名無し 25/12/01(月)21:53:34No.537403+📌 固定電話を登録する手順 |
| … | 22無題Name名無し 25/12/01(月)21:54:41No.537404+SMS が使えない固定電話の場合、Google が自動音声通話をかけてきて、確認コードを読み上げます。 |
| … | 23無題Name名無し 25/12/01(月)21:55:45No.537405+💡 まとめると、固定電話を登録する場合は「音声通話でコードを受け取る」形になります。携帯がなくても本人確認は可能です。 |
| … | 24無題Name名無し 25/12/01(月)21:56:31No.537406+名前(姓・名) |
| … | 25無題Name名無し 25/12/01(月)21:57:08No.537407+⚠️ 注意点 |
| … | 26無題Name名無し 25/12/01(月)21:57:41No.537408+👉 実際に「固定電話で音声通話認証する手順」をさらに詳しく説明しましょうか? |
| … | 27無題Name名無し 25/12/01(月)21:58:14No.537409+✅ 電話番号入力画面の出し方(手順) |
| … | 28無題Name名無し 25/12/01(月)21:58:43No.537410+⚠️ 注意点 |
| … | 29無題Name名無し 25/12/01(月)21:59:16No.537411+✅ ブラウザを変える方法 |
| … | 30無題Name名無し 25/12/01(月)21:59:50No.537412+👉 今お使いの端末は タブレット(Android / iPad)ですか?それとも PC(Windows / Mac)ですか?それによって、具体的なブラウザ切り替え手順を詳しく説明できますよ。 |
| … | 31無題Name名無し 25/12/01(月)22:00:06No.537413+Chrome 👉 Google Chrome ダウンロードページ 「ダウンロード」ボタンを押してインストールします。 |
| … | 32無題Name名無し 25/12/02(火)18:26:04No.537446+https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount |
| … | 33無題Name名無し 25/12/04(木)18:49:32No.537569+西武技研 助川電気工業 ノベーションなどの新しい時代に向けた技術革新に資するものをもった企業でしょうか? |
| … | 34無題Name名無し 25/12/04(木)18:52:22No.537570+助川電気工業:核融合・次世代原子炉・半導体製造など“極限環境”の計測・加熱技術 → 国家戦略級のエネルギー・半導体分野で存在感を増す企業 |
| … | 35無題Name名無し 25/12/04(木)18:58:07No.537571+大気中CO₂を濃縮し農作物の収量向上に貢献 |
| … | 36無題Name名無し 25/12/04(木)19:00:16No.537572+📊 3. 両社の比較(イノベーション観点) |
| … | 37無題Name名無し 25/12/04(木)19:02:18No.537573+アメリカ企業のマーベル・テクノロジーも、新しい時代向けの企業のようですが、何をしていますか? |
| … | 38無題Name名無し 25/12/04(木)19:03:22No.537574+高速データ転送用のインターコネクト |
| … | 39無題Name名無し 25/12/04(木)19:04:18No.537575+光相互接続スタートアップ「Celestial AI」を約32.5億ドルで買収 |
| … | 40無題Name名無し 25/12/04(木)19:05:37No.537576+マーベルは、クラウド企業向けにカスタムシリコンを提供し、AIインフラを最適化しています。 |
| … | 41無題Name名無し 25/12/04(木)19:12:38No.537577+気になることして、meta社のAIチームや、エヌヴィデアのスタッフに、中国人、それも、中国の大学卒業者で北米大学留学生でない物を大量採用していませんか? |
| … | 42無題Name名無し 25/12/04(木)19:13:53No.537578+NVIDIAも、中国系AI研究者が世界のAI研究者の約50%を占めるとCEOが発言しており、同社にも多く在籍しているとされています。 |
| … | 43無題Name名無し 25/12/04(木)19:15:33No.537579+✅ 出身大学 |
| … | 44無題Name名無し 25/12/04(木)19:17:05No.537580+ただし、NVIDIAはAI半導体の中心企業であり、 |
| … | 45無題Name名無し 25/12/04(木)19:18:44No.537581+中国のトップ大学(清華・北大・USTC)は数学・物理・情報科学が世界トップレベル |
| … | 46無題Name名無し 25/12/04(木)19:19:52No.537582+必要であれば、 ✅ なぜ中国系AI研究者が世界を席巻しているのか ✅ 米国政府の規制(ビザ・安全保障) ✅ MetaやNVIDIAの採用戦略の背景 ✅ 日本企業との比較 |
| … | 47無題Name名無し 25/12/04(木)19:21:06No.537583+🌏 インド系研究者が多い理由 |
| … | 48無題Name名無し 25/12/04(木)19:23:35No.537584+数学・物理・哲学など抽象思考を重視する伝統 |
| … | 49無題Name名無し 25/12/04(木)19:24:19No.537585+もし興味があれば、 ✅ どの企業にどの系統の研究者が多いのか ✅ なぜAI分野は特定の国籍に偏りがちなのか ✅ 日本がAI人材で遅れている理由 |
| … | 50無題Name名無し 25/12/04(木)19:25:52No.537586+✅ 1. 「中国国籍者は国家に協力義務がある」というのは事実か? |
| … | 51無題Name名無し 25/12/04(木)19:27:04No.537587+✅ 2. では、海外にいる中国国籍者も対象になるのか? |
| … | 52無題Name名無し 25/12/04(木)19:28:13No.537588+✅ ユダヤ系 |
| … | 53無題Name名無し 25/12/04(木)19:29:13No.537589+✅ ② 人質リスク |
| … | 54無題Name名無し 25/12/04(木)19:30:54No.537590+✅ ② 中国国籍者の採用は“慎重化” |
| … | 55無題Name名無し 25/12/04(木)19:31:40No.537591+もちろん、ここからは 「アメリカが中国人研究者・中国企業に対してどのような規制を行っているか」 を、できるだけ体系的にまとめていきます。 これは今まさに世界の技術地図を変えている重要テーマです。 |
| … | 56無題Name名無し 25/12/04(木)19:34:33No.537592+● 研究プロジェクトへのアクセス制限 |
| … | 57無題Name名無し 25/12/04(木)19:36:19No.537593+● AIチップの対中輸出規制 |
| … | 58無題Name名無し 25/12/04(木)19:38:02No.537594+● 中国企業の米国上場審査の強化 |
| … | 59無題Name名無し 25/12/04(木)19:39:16No.537595+あなたが述べたように、 |
| … | 60無題Name名無し 25/12/04(木)19:40:15No.537596+✅ ● シンガポール拠点を大幅強化 |
| … | 61無題Name名無し 25/12/04(木)19:49:53No.537597+● 中国拠点は縮小(検索結果で明確に確認) |
| … | 62無題Name名無し 25/12/04(木)19:59:57No.537598+✅ ② Marvellの技術中核は「イスラエル・米国・インド」 |
| … | 63無題Name名無し 25/12/04(木)20:00:46No.537599+Meta非常に高い低いAI研究者の約50%が中国系 |
| … | 64無題Name名無し 25/12/04(木)20:01:23No.537600+必要であれば、 ✅ Marvellの将来性 ✅ NVIDIAとの比較 ✅ 投資観点での分析 ✅ 米中対立が半導体企業に与える影響 |
| … | 65無題Name名無し 25/12/04(木)20:02:15No.537601+1. マーベルの将来性(ビジネスとしてのポジション) |
| … | 66無題Name名無し 25/12/04(木)20:02:47No.537602+最新では、NVIDIAと組んでNVLink Fusionをマーベルのカスタムシリコンに統合する提携も発表しており、“NVIDIAの敵”というより“AIインフラの同盟企業”の位置づけです。 |
| … | 67無題Name名無し 25/12/04(木)20:04:19No.537603+対中規制の影響A100/H100輸出規制の直撃中国依存が低く、影響は限定的 |
| … | 68無題Name名無し 25/12/04(木)20:05:37No.537604+イスラエル |
| … | 69無題Name名無し 25/12/04(木)20:06:42No.537605+マーベルの現在の動きを見ると、 |
| … | 70無題Name名無し 25/12/04(木)20:08:47No.537606+5. 将来性まとめ(個人的な見立て) |
| … | 71無題Name名無し 25/12/04(木)20:14:49No.537607+っしゃる視点は非常に鋭いです。EVをめぐる議論は「環境政策」「産業政策」「消費者行動」の三つが絡み合っていて、報道や政策がしばしば短期的な補助金頼みになってしまったのは確かです。整理すると👇 |
| … | 72無題Name名無し 25/12/04(木)20:16:03No.537608+🚉 EVの本質:「線路のない電車」 |
| … | 73無題Name名無し 25/12/04(木)20:17:16No.537609+✅ まとめ |
| … | 74無題Name名無し 25/12/04(木)20:26:06No.537610+はい、その見方はかなり現実的です。トヨタの近年の動きを整理すると、従来の「自動車メーカー」から「モビリティ・インフラ企業」への転換を模索しているように見えます👇 |
| … | 75無題Name名無し 25/12/04(木)20:27:07No.537611+将来的には都市内の移動を「地上+空中」で統合するモビリティサービスを提供する可能性。 |
| … | 76無題Name名無し 25/12/04(木)20:28:24No.537612+✅ まとめ |
| … | 77無題Name名無し 25/12/04(木)20:29:23No.537613+では「トヨタが公共交通・インフラ型ビジネスに転換した場合、日本の他産業との連携がどう広がるか」を整理してみましょう👇 |
| … | 78無題Name名無し 25/12/04(木)20:30:46No.537614+📡 通信産業との連携 |
| … | 79無題Name名無し 25/12/04(木)20:34:50No.537615+🚉 公共交通との連携 |
| … | 80無題Name名無し 25/12/06(土)14:34:14No.537628+「日本称賛系」「中国批判系」などの動画制作案件、報酬金額は◯◯◯◯円だった… |
| … | 83無題Name名無し 25/12/15(月)19:27:08No.537700+中世日本のミニミニ共和国戦争!琵琶湖湖岸集落の抗争 |
| … | 84無題Name名無し 25/12/15(月)19:54:56No.537701+異星人のお婿さんに選ばれました。 |
| … | 85無題Name名無し 25/12/18(木)21:15:15No.537702+【調査】初音ミクをNHK紅白歌合戦に出演させる方法を考えてみた |
| … | 86無題Name名無し 25/12/19(金)20:56:53No.537703+MMD しゅお |
| … | 87無題Name名無し 25/12/21(日)15:46:24No.537714+あなたがいた証【ボイスロイド劇場】【日常系】 |
| … | 88無題Name名無し 25/12/21(日)19:49:25No.537715+超兄貴 りりせ ことね ふたば |
| … | 89無題Name名無し 25/12/22(月)15:33:25No.537716+ゆずきず誕生祭 |
| … | 91無題Name名無し 25/12/23(火)12:20:28No.537720+https://hochi.news/articles/20251219-OHT1T51032.html |
| … | 92無題Name名無し 25/12/26(金)19:01:59No.537739+【微コッ…】<幕間> 六花「今日、財布落としちゃってさぁ〜笑」【Cevio劇場】 |
| … | 94無題Name名無し 26/02/01(日)19:45:55No.537938+本当にいい男 |