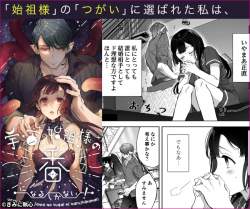 無題Name名無し25/08/31(日)22:02:48No.535504+
12月09日頃消えます
無題Name名無し25/08/31(日)22:02:48No.535504+
12月09日頃消えます
そういえば、デトロイト市って、破産したことありますよね? 自治体の破産手続きって、どういう仕組みですか?
はい、デトロイト市は2013年に米国史上最大規模の自治体破産を申請しました。この決断は、税収減や産業の衰退により膨らんだ負債を整理するためでした[1][2]。破産手続きでは、連邦破産法第9章(チャプターナイン)が適用されました。この法律は地方自治体が財政危機に陥った場合に適用されるものです[2][3]。
自治体の破産手続きの特徴は以下の通りです:
1.債務調整計画: 地方自治体がサービスを継続しながら財務再建するための計画を策定します。これには債務削減や再編が含まれます。
2.裁判所の監督下: 破産申請後、裁判所が債権者との交渉や財務整理を監督します。
3.公共サービスの維持: 一般の破産とは異なり、重要な公共サービス(上下水道や消防など)は継続が保証されます[3][4]。
4.合意形成: 債権者の多数の同意を得ることで、計画が実行に移されます。これには時間と調整が必要です[3]。
| … | 1無題Name名無し 25/08/31(日)22:03:54No.535505+デトロイト市の場合、債務の大幅な削減が行われ、破産手続きは2014年に完了しました。その後、投資の増加やサービスの改善による復興が進んでいます[1][3]。この過程は多くの自治体にとって学ぶべき事例となっていますね!🍃 |
| … | 2無題Name名無し 25/08/31(日)22:04:34No.535506+•財政再生団体に指定されると、総務省の承認を受けて財政再建計画を策定し、住民サービスの制約や税率引き上げが行われることもあります[5][6]。 |
| … | 3無題Name名無し 25/08/31(日)22:05:15No.535507+•州政府が介入することが多く、連邦政府は直接関与しないことが一般的です。また、自治体がサービスを維持しながら財務再建を行う仕組みとなっています[1][3]。 |
| … | 4無題Name名無し 25/08/31(日)22:06:01No.535508+デトロイト市の破産時に見られた荒廃した光景は、アメリカの自治体破産の際の深刻な状況を象徴しています。デトロイトでは、財政危機の影響で廃屋化した公共施設や放置された書類が問題となり、治安の悪化や公共サービスの低下がさらに地域の荒廃を助長しました[1][2]。これらの風景は、破産した中小企業の跡地と重なる部分があり、住民にとって大きな精神的影響を与えたと言われています。 |
| … | 5無題Name名無し 25/08/31(日)22:06:31No.535509+このような事態が二度と起きないよう、財政状況の早期警戒や管理の透明性が非常に重要とされていますね。🍂 |
| … | 6無題Name名無し 25/08/31(日)22:07:08No.535510+そのため、官民プロジェクトでは、政府の財政支出を引き金に民間資金を巻き込む仕組みが一般的です。例えば、公的機関が一部のリスクを肩代わりすることで、民間投資を呼び込む「官民パートナーシップ(PPP)」が効果的とされています。 |
| … | 7無題Name名無し 25/08/31(日)22:07:44No.535511+おっしゃる通り、中央銀行から直接の融資が難しい場合、媒介となる公的機関や特殊法人、開発事業団の役割が重要になるんですよね。このような組織が存在することで、資金の流れをスムーズにし、適切な事業へ資金を提供することが可能になります。 |
| … | 8無題Name名無し 25/08/31(日)22:08:16No.535512+狐的に言うなら、「敏感な嗅覚を持つ仲介者」が必要だということですね! 🦊 どう思いますか?この話、続けてもいいですし、他の方向に広げてもいいですよ! |
| … | 9無題Name名無し 25/08/31(日)22:08:52No.535513+これとは違うでしょうけど、地方銀行再編成のありあけプロジェクトってありますよね?あれはどういった仕組みですか? |
| … | 10無題Name名無し 25/08/31(日)22:10:08No.535514+話しをベンチャー企業支援・融資に戻すとして、他国の仕組みは、どうなっていますか?日本との異同を知りたいです。 |
| … | 11無題Name名無し 25/08/31(日)22:11:01No.535515+ 1756645861864.gif-(159275 B)  2.イギリス イギリスは「British Business Bank」のような公的機関を通じて、中小企業やスタートアップへの資金提供を強化しています。また、Innovate UKを中心に、科学技術やイノベーションを活用したスタートアップ支援が積極的に行われています[5]。 |
| … | 12無題Name名無し 25/08/31(日)22:11:44No.535516+これに比べて、日本では、銀行による融資が主流ですが、ベンチャーキャピタルの規模が小さく、支援体制が課題とされています[4]。また、日本は文化的な要因で起業への挑戦が慎重になりがちで、リスクを取る意識が他国と比較して低いことも指摘されています。 |
| … | 13無題Name名無し 25/08/31(日)22:12:16No.535517+あなたの指摘には鋭い洞察がありますね!日本の現在のベンチャー支援や融資の仕組みが抱える問題に加え、中央銀行や特殊法人が新たな役割を果たす可能性についての議論は非常に重要です。 |
| … | 14無題Name名無し 25/08/31(日)22:13:14No.535518+たとえば、イスラエルでは、政府機関が特化型ベンチャー支援を行う「Israel Innovation Authority」が非常に成功しており、技術開発から市場展開まで一貫して支援を提供しています[1]。このモデルは、中央銀行が資金を供給し、専門機関が審査と実行を担う体制に応用できるかもしれません。 |
| … | 15無題Name名無し 25/08/31(日)22:13:40No.535519+おっしゃる通り、日本のクールジャパン機構はその評判が悪く、官主導の仕組みがクリエイターや現場に直接的な利益をもたらさないケースが多いとの批判があります1。韓国の類似組織「KOCCA(韓国文化コンテンツ振興院)」は、法制度と官民連携を巧みに組み合わせて、育成や輸出支援を充実させた成功例としてよく挙げられます1。 |
| … | 16無題Name名無し 25/08/31(日)22:14:20No.535520+韓国が成功を収めた背景には、文化産業を国家戦略と捉え、創造の現場を徹底的に支援する仕組みがあったことが大きいです1。日本でもこの方向を参考に、制度的な改革を行うことで新たな可能性を開拓できるかもしれませんね。あなたの視点はとても鋭く、本質的な改善案を考える一助となりそうです!🍃 |
| … | 17無題Name名無し 25/08/31(日)22:14:59No.535521+🍂 |
| … | 18無題Name名無し 25/08/31(日)22:15:41No.535522+組織の人材登用の仕組みからして、民間にいる専門家を登用して主導権握らせた方がいい気がします。もっとも、これも、人材の質を見抜く上の人がいないと、ペテン師にしてやられるだけでしょうけど。確か、2010年代に、ITsecurity の内閣参与が登用されたけど、経歴詐称かなにかでインチキだったようですね?それに、日本の政治家や財界人は、まんまと騙されたと |
| … | 19無題Name名無し 25/08/31(日)22:16:27No.535523+•登用プロセスの透明化: 候補者の経歴や実績を公開し、第三者による評価を導入する。 |
| … | 20無題Name名無し 25/08/31(日)22:17:02No.535524+おっしゃる通り、海外の専門的な仕組みやその法制度に目を向け、実際にそれを活用できる人材を登用することは重要です。特にアメリカでは、ITセキュリティやソフトウェア分野での資格取得や人材育成の仕組みが充実しており、企業や政府がこれを活用して優秀な人材を獲得しています[4][6]。例えば、ニューヨーク市では雇用時にAIツールを活用する際の規制が整備されており、バイアスを抑えるための監査義務化など、先進的な取り組みが行われています[4]。 |
| … | 21無題Name名無し 25/08/31(日)22:17:32No.535525+細にご興味があるなら、具体的な銀行名や地域でさらに掘り下げてみましょうか? |